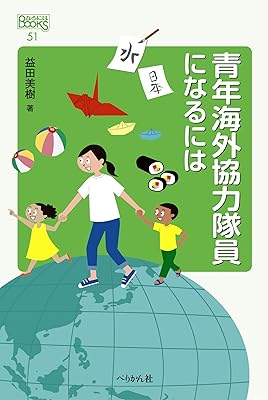はる
はる¡Hola, bienvenida! いらっしゃいませ!
はるカタルニャです。



本日は「中東のカントリーカフェ」となっております!
ご来店いただき本当にありがとうございます。
今回は、青年海外協力隊の派遣国の中でも、「幸福のアラビア」と称された豊かな歴史を持つ【イエメン】に焦点を当てます。しかし、まず最も重要なことをお伝えしなければなりません。
この記事は、過去の隊員たちの活動に敬意を表し、未来に平和が訪れ派遣が再開される日を願って、イエメンという国の本来の文化や歴史、そしてかつての協力隊の姿を記録としてお届けするものです。
- 青年海外協力隊の「イエメン派遣」の歴史に関心がある方
- 紛争前のイエメンの文化や生活情報を知りたい方
- 将来、復興支援などでイエメンと関わることを考えている方
- 国際協力や人道支援に関心があり、イエメンという国について深く学びたい方
- イエメンの平和な日常が戻ることを願い、現地の情報を収集したい方



イエメンも、今は協力隊は行けないんだ…。



昔はどんな活動をしていたんだろう?



平和になったら、どんな国なんだろう…?
残念ながら、現在は渡航することさえ極めて困難な状況です。
実はこのブログを書いている私も、いつか青年海外協力隊員として世界に貢献したいと夢見ています。だからこそ、今は活動できなくても、イエメンという国の本来の姿や文化を知り、平和な未来を考えることが大切だと感じています。
この記事では、未来の平和なイエメンを思い描きながら、あなたが知りたいであろう情報を、同じ目線でリサーチし、ギュッと詰め込みました。
- (紛争前の)イエメンという国の魅力と基本情報(歴史、文化、言語、気候など)
- (過去の)青年海外協力隊員としての具体的な活動内容や求められたスキル
- (紛争前の)現地でのリアルな生活(住居、食事、物価まで網羅!)
- (将来派遣が再開された場合の)応募から派遣までの一般的な流れ
- 現在の極めて厳しい治安情報と安全に関する重要な注意喚起
この記事は、イエメンへの渡航を推奨するものでは決してありません。むしろ、現在のイエメンが置かれた人道上、極めて深刻な状況を正確に理解しつつ、世界遺産にも登録された独自の文化や歴史を知ることで、国際協力や平和について考えるきっかけになることを願っています。
ぜひ最後までじっくりお読みいただき、イエメンという国への理解を深めてください。


イエメン派遣の基本情報:概要・特徴・言語を徹底解説!


ここでは、青年海外協力隊が派遣されていた、紛争前のイエメンがどのような国だったのか、その基本的な情報をご紹介します。



中東にあるって聞いたけど、具体的にどこ?
周りの国とはどんな関係なの?



砂漠のイメージだけど、農業も盛んだったって本当?
季節による寒暖差は激しいんだろうか?



英語は通じるの?
やっぱりアラビア語が話せないとダメかな。
そんな疑問に答えるべく、平和だった頃のイエメンの基本情報から、変化に富んだ気候、コミュニケーションの鍵となる言語、そして心に触れる文化や習慣まで、徹底的にご紹介します!
イエメンの本来の姿を理解し、平和な未来を願うための知識を、分かりやすく丁寧にお伝えしますのでご覧ください!
イエメン共和国ってどんな国?まず知りたい基礎知識まとめ
イエメンの首都、言語、通貨、時差、気候、電圧、日本からのアクセス方法など、紛争前の基本情報を分かりやすくまとめました。
| 国(首都) | イエメン共和国(サヌア)※暫定首都はアデン |
|---|---|
| 言語 | アラビア語(公用語)。ソコトラ語など地域言語も使用。 |
| 通貨 | イエメン・リヤル(YER)。※内戦により価値は著しく下落。 |
| 時差(サマータイム) | 日本より6時間遅れ。サマータイムなし。 |
| 気候 | 砂漠気候、ステップ気候、熱帯高地気候が混在 |
| 電圧 | 230ボルト / 50ヘルツ |
| コンセント | A, D, Gタイプなどが混在。変換プラグが必須。 |
| 面積 | 約52.8万平方キロメートル(日本の約1.4倍) |
| 産業 | (紛争前は)石油・天然ガス、農業(コーヒー、カート)、漁業など。 |
| 直行便(2025年9月現在) | なし。※現在、日本からの渡航は極めて困難。 |
| 日本からの行き方 | (紛争前は)中東の主要都市を経由するのが一般的だった。 |
実は直行便よりも乗り継ぎ便の方が航空券は安いことが多いです!
また、航空券を比較してから予約したい場合は、安くて24時間対応の「Trip.com」を愛用しています。
以前ボスニア・ヘルツェゴビナで携帯を盗まれた際、「Trip.com」の日本語チャットサポートが迅速で、本当に助けられました。
- お得な料金で見つかりやすい
- 24時間日本語サポートで安心
- トラブル時も迅速に対応
海外旅行の際は、ぜひ「Trip.com」をチェックしてみてください!
イエメンの面積は?日本の約1.4倍
さて、かつて青年海外協力隊の派遣国であった『イエメン』ですが、その広さは一体どのくらいなのでしょうか?
イエメンの面積は 約52.8万平方キロメートル。と言っても、数字だけではピンと来ないかもしれませんが、日本と比較してみると…



実は、日本の国土の約1.4倍!



その中に、世界遺産の旧市街や独自の生態系を持つ島など、多様な魅力が詰まっていたんです!
隣国は?サウジアラビアとオマーン
また、アラビア半島の南西端に位置するイエメン。
この国がどのような地理的環境にあり、それが文化や経済にどんな影響を与えているのか、その輪郭もGoogleマップで見ていきましょう。
イエメンは、北にサウジアラビア、東にオマーンと国境を接し、紅海、アデン湾、アラビア海に面しています。
古くからインド洋交易の要衝として栄え、「幸福のアラビア」と呼ばれた豊かな歴史を持っていました。



イエメンは海にも面しているんですね。



モカコーヒー発祥の地としても知られ、山岳地帯では今もコーヒーが栽培されています!
このように、多様な隣国に囲まれた地理的な特徴は、イエメンの豊かな文化を育む土壌となってきました。
そして、その文化をより深く理解する上で欠かせないのが、『気候』と人々のコミュニケーションを支える『言葉』です。
それでは、イエメンの日々の気候と、普段の生活で人々がどのような言語を使い、心を通わせているのか、その興味深い『気候・言語事情』を一緒にみていきましょう!
イエメンの気候を徹底解説!年間を通じた特徴と季節ごとの注意点



イエメンの気候は、地域によって大きく異なり、紅海沿岸部は高温多湿、山岳地帯は温暖で過ごしやすく、内陸部は典型的な砂漠気候です。
特に首都サヌアなどの山岳地帯は、標高が高いため一年を通して比較的過ごしやすいものの、一日の寒暖差が非常に大きいのが特徴です。
季節は大きく乾季と雨季に分かれ、それぞれに備えた服装の準備が快適な生活の鍵となります。
- 乾季(10月~3月頃)
雨はほとんど降らず、過ごしやすい季節です。しかし、山岳地帯では朝晩はかなり冷え込み、冬には0℃近くまで気温が下がることもあります。 - 雨季(4月~5月、7月~9月頃)
二度の雨季があり、短時間に激しい雨が降ることがあります。日中の気温は30℃を超えることもあり、蒸し暑くなります。
服装は、滞在する地域と季節に合わせて準備する必要があります。特に山岳地帯に長期滞在する場合は、夏服だけでなく、フリースやジャケットなどの防寒着も必須です。重ね着で体温調節ができるようにするのがベストです。また、年間を通じて日差しが非常に強いため、帽子やサングラス、日焼け止めでの紫外線対策は必須です!
イエメンの言語事情:英語は通じる?公用語と現地の言葉



イエメンでは何語がメインなの?



英語はどの程度通用するの?
といった、イエメンの言葉に関する疑問は多いはず。
イエメンの公用語から現地で話される多様な言語まで、その実態を分かりやすく解説します。
これを読めば、イエメンでのコミュニケーションのイメージがグッと具体的になるはずです!
イエメンで使われている言語の種類|公用語はアラビア語
イエメンの公用語はアラビア語です。しかし、地域によって方言差が大きく、独自の言語も話されています。
特に、世界遺産にも登録されているソコトラ島では、古代南アラビア語の生き残りともいえる固有言語「ソコトラ語」が話されており、言語学的にも非常に貴重な地域です。
- アッサラーム・アライクム: こんにちは
- シュクラン: ありがとう
協力隊員として活動する上では、公用語であるアラビア語、特に現地で話される口語(アンミーヤ)を学ぶことが、現地の人々と心を通わせるための大切な鍵となります。
豆知識ですが、国名の由来とされる「ヤマン(右)」は、古代の地図で南を右に置いたことから、「ユムン(肥沃な)」は、雨の多い気候から「幸福のアラビア」と呼ばれた歴史に由来すると言われています。
青年海外協力隊員は英語で活動できる?|現地での英語通用度



紛争前の状況では、首都サヌアやアデンなどの都市部や一部のホテルを除き、英語はほとんど通用しませんでした。
青年海外協力隊の活動においても、配属先の同僚とのやり取りや地域住民との交流は、基本的にアラビア語で行われていました。
そのため、もし将来派遣が再開されることがあれば、派遣前訓練や現地での語学習得が非常に重要になります。
基本的なアラビア語を話せることで、人々の心が一気に開かれ、より深く、温かい関係を築くことができるでしょう。
言語の壁を乗り越える努力は、国際協力の第一歩と言えるでしょう。


イエメン派遣の職種と活動内容|青年海外協力隊の専門性を解説!
ここでは、過去に青年海外協力隊がイエメンでどのような活動を行っていたのか、その歴史を振り返ります。



昔、イエメンに派遣されていた協力隊員は、どんな活動をしていたんだろう?



どんなスキルや経験が役立っていたのかな…。
この記事を読み進めれば、平和だった頃のイエメンで、実際にどのような職種があり、どんな専門性が求められていたのかが具体的に分かります。
未来の復興を担うかもしれない、あなたの挑戦のヒントがここにあるかもしれません。
イエメン派遣の現状:最新の隊員数と派遣実績データ(男女別・累計)
まず、青年海外協力隊のイエメンへの派遣実績(2025年3月31日現在)をご紹介します。
JICAの公式データによると、以下のような内容となっています。
派遣中隊員数: 0名(うち女性0名)
帰国隊員数 : 68名(うち女性 29名)
累計派遣隊員数: 68名(うち女性 29名)
※1990年代後半から派遣が停止されており、その後も情勢不安により再開されていません。このデータは、それ以前に活動した隊員の方々の累計です。
イエメンで求められていた専門性:人気の派遣職種と具体的な活動事例



紛争前のイエメンでは、どんな分野でボランティアが求められていたの?



どんな職種で活躍していたんだろう?
そんな疑問にお答えします!
かつてイエメンで青年海外協力隊員が活躍していた、主要な活動分野は以下の通りです。
- 保健・医療: 看護師や助産師、臨床検査技師など、特に母子保健の分野で、医療サービスの質の向上や、人々の健康を支える活動が行われていました。
- 教育: 自動車整備や電気、コンピュータ技術などの職業訓練指導員として、若者の技術力向上に貢献していました。
- 農業・水産: 野菜栽培や漁業指導などを通じて、食料生産の安定や農漁村の生活改善を支援する活動が求められていました。
- スポーツ: 柔道や空手など、様々なスポーツの指導を通じて、青少年の健全な育成に貢献していました。
引用:JICAイエメン事務所
より具体的な活動内容や、過去に派遣された隊員の体験談に興味がある方は、JICA公式サイトの過去の報告書などを探してみることをお勧めします。


(紛争前の)イエメンでの生活基盤:協力隊員の住居とインフラ事情
ここでは、紛争前の平和な時代、青年海外協力隊員がどのような住居で生活し、現地のインフラとどのように向き合っていたのか、その様子を振り返ります。



安心して活動に打ち込むためにも、快適で安全な住環境と、安定したライフラインの確保が欠かせません。
ここからは、かつて隊員が実際にどのような住居で生活し、現地のインフラとどのように向き合っていたのか、その実情を詳しくご紹介させていただきます!
イエメンでの住まいはどうだった?協力隊員の住居事情



青年海外協力隊員の住居は、JICAが隊員の安全と健康を最優先に考えて手配していました。
イエメンでは、首都サヌアや地方都市において、アパートや一軒家を借りて生活することが一般的でした。
- アパート・一軒家
キッチン、シャワー、トイレなどが完備された住居が提供されていました。停電や断水に備え、自家発電機や貯水タンクが設置されていることもありました。 - 伝統的な住居
世界遺産サヌア旧市街に代表される、美しい装飾が施された塔状の家屋はイエメン建築の象徴です。隊員が住むことは稀でしたが、イエメンの文化を肌で感じられる貴重な景観でした。
※現在のイエメンでは、紛争により多くの住居が破壊され、インフラも深刻なダメージを受けています。
電気・水道・インターネットは?イエメンのインフラ整備状況



また、紛争前のイエメンでの生活でも、日本のインフラ環境との違いを実感する場面が多くありました。
- 電気
都市部でも計画停電は日常的で、1日のうち数時間しか電気が使えないことも珍しくありませんでした。 - 水道
水道水の供給も不安定で、断水が頻繁にありました。多くの家庭では屋上に貯水タンクを設置し、水を貯めて使っていました。 - インターネット
紛争前は、都市部を中心にダイヤルアップ接続やADSLが普及し始めていましたが、回線は遅く不安定でした。



昔から、インフラは大変だったんですね…。
平和な日常がいかに貴重であるかを痛感させられます。一日も早く、安定したインフラが復旧し、人々が安心して暮らせる日が来ることを願わずにはいられません。
そのために不可欠なのが、まさに「命綱」とも言える大容量モバイルバッテリーです。



私が使っているこれは、スマホを何回もフル充電できる大容量なのにコンパクトでおすすめです!
頻繁に起こる停電の中でも、スマートフォンの充電を気にせず使える安心感は絶大ですね。


イエメン生活のリアル体験!物価・治安・服装から文化まで徹底解説
ここでは、紛争前のイエメンでの生活に直結する「お金のこと」や当時の「安全のこと」について、過去の情報を基に解説します。現在の状況とは大きく異なることをご理解の上、お読みください。



昔のイエメンの物価って、どんな感じだったんだろう?



日本とは違う文化や習慣がたくさんありそうだけど、どんなことに気をつければよかったのかな?



紛争前は、治安は良かったの?



気をつけるべきことって何だろう…?
そんな疑問に答えるべく、このセクションではイエメンの通貨「リヤル」の基本情報から、紛争前の物価水準、そして当時の治安状況や文化的な注意点まで、あなたが平和だった頃のイエメンを知るための情報を分かりやすく解説します。
イエメンの通貨「リヤル(YER)」の基本と(紛争前の)リアルな物価事情
イエメンの通貨は「イエメン・リヤル(Yemeni Rial)」で、略称は「YER」です。
紛争前は比較的安定していましたが、2015年以降の紛争と経済封鎖により、通貨価値は著しく下落し、ハイパーインフレーションと深刻な食糧危機が続いています。
以下は、紛争前の物価のイメージです。現在の物価とは全く異なる点にご注意ください。
| 水(1.5L) | 約50 YER |
| ホブス(パン)1枚 | 約10 YER |
| 市内の食堂(1食) | 約300~500 YER |
| 乗り合いバス(市内) | 約20 YER |
※紛争前は、日本と比べると物価は非常に安く、特に食料品や交通費は手頃な価格でした。しかし現在、国民の大多数が人道支援を必要としており、食料の確保さえ困難な状況にあります。
イエメンの治安状況|外務省危険レベルと協力隊員の安全対策



極めて重要なお知らせです。現在のイエメンの治安は、極度に悪化しています。
2025年9月現在、外務省の海外安全情報では、イエメン全土に最高レベルの「レベル4:退避してください(退避勧告)」が発出されています。これは、どのような目的であれ、渡航は絶対に止めてくださいという強い勧告です。
紛争前も、部族間の対立やテロ、誘拐事件などが発生しており、協力隊員は厳格な安全対策の下で活動していました。しかし、2015年以降の状況はそれとは比較にならないほど悪化し、国全体が人道危機のただなかにあります。
当然ながら、JICAは青年海外協力隊をこのような危険な地域に派遣することはありません。
イエメンへの渡航は、いかなる理由があっても絶対に止めてください。最新の情報は必ず「外務省の海外安全情報」をご確認ください。
この記事で紹介する文化や習慣は、平和だった頃のイエメンの姿です。現在の危険な状況とは切り離して、文化理解の一助としてお読みください。
引用:外務省の海外安全情報
引用:イエメン安全対策基礎データ
(紛争前の)イエメン生活での服装ガイド|普段着の選び方と民族衣装の魅力



服装に関する疑問は、その国の文化を知る上でとても大切なポイントになりますよね。
ここでは、平和だった頃のイエメンで、人々がどのような服装をしていたのか、そして協力隊員が活動する上でどのような配慮が必要だったのかを解説します。
日々の活動や生活シーンに合わせた、具体的な服装選びのポイントから詳しく見ていきましょう。
シーン別・イエメンでの最適服装ガイド|普段着から活動時まで徹底解説
紛争前のイエメンでの服装は、保守的なイスラム文化への配慮と、地域による気候差、そして一日の大きな寒暖差への対策がポイントでした。
- 肌の露出は厳禁
特に女性は、体のラインが出ない、ゆったりとした服装が求められました。外出時には「アバヤ」と呼ばれる黒い外套と、「ヒジャブ」で髪を覆うのが一般的でした。 - 男性も長ズボンが基本
男性も、半ズボンなどの肌の露出が多い服装は避け、長ズボンを着用するのがマナーでした。 - 重ね着で寒暖差に対応
特に山岳地帯では、日中は暑くても夜は冷え込むため、簡単に着脱できる上着は必須でした。 - 日差し対策を忘れずに
年間を通して日差しが強いため、帽子、サングラス、UVカット機能のある羽織りものなどは必須アイテムでした。



文化への配慮がとても重要だったんですね!
イエメン男性の誇り「ジャンビーア」
イエメンの男性を象徴するのが、「ジャンビーア」と呼ばれる半月状の短剣です。
これは武器としてではなく、成人男性の証であり、家柄や誇りを示す装飾品として、腰のベルトに差すのが伝統的なスタイルでした。
協力隊員も、このジャンビーアを通じて、イエメンの部族社会や男性の価値観に触れる機会があったかもしれません。



服装一つにも、深い文化が根付いているんですね。
(紛争前の)イエメン文化に触れる:習慣・マナーで気をつけること
ここでは、平和だった頃のイエメンで大切にされていた文化や習慣について解説します。異文化の中で生活する上で、こうした習慣やマナーの理解は非常に重要でした。



イエメンでは、どんなことに気をつければよかったんだろう?日本とは全然違うのかな?



カートっていう葉っぱを噛む習慣があるって本当?



もしかして、日本人の感覚だと『えっ?』と思うような習慣もあったのかな…?
イエメンには、私たちが知っておくべきユニークで大切な文化や習慣がたくさんありました。
ここでは、イエメンの人々とのコミュニケーションを円滑にするための具体的なポイントを解説します。
過去のイエメンの豊かな文化を知り、平和な未来を考えるための「イエメン文化の心得」を一緒に学びましょう!
イエメンで守るべき基本的なマナー|日常生活での注意点
- 部族のルールを尊重
イエメン社会は、イスラム教の教えと共に、古くからの部族の慣習やルールが非常に強く根付いていました。部族の結束を重んじる文化への理解が不可欠でした。 - 左手は不浄
イスラム文化では左手は不浄なものとされていたため、食事の際や物の受け渡し、握手の際には必ず右手を使うようにしていました。 - 写真撮影の許可
特に女性や部族の長老などを撮影する際は、必ず事前に許可を取っていました。無断でカメラを向けることは、大きなトラブルの原因になりかねませんでした。 - 男女間の距離感
保守的な社会であるため、公共の場で男女が親しく話したり、体に触れたりすることは避けられていました。異性との接し方には細心の注意が必要でした。



部族のルールが優先されることもあるんですね!
午後のコミュニケーション「カート・タイム」
イエメンの午後の日常に欠かせないのが、「カート」と呼ばれる植物の葉を噛む習慣です。
カートには軽い興奮作用があり、男性たちが集まってカートを噛みながら談笑する時間は、重要な情報交換や社交の場となっていました。
協力隊員も、この「カート・タイム」に招かれることを通じて、地域社会の人間関係を理解し、信頼を築いていくことがありました。一方で、カート栽培による水資源の枯渇や健康への影響は、当時のイエメンが抱える課題の一つでもありました。


(紛争前の)イエメンの食文化を味わう!代表的な料理と食事のポイント
歴史的に「幸福のアラビア」と呼ばれたイエメンは、多様な文化の影響を受けた、豊かで奥深い食文化を誇っていました。



平和だった頃のイエメンでは、どんなものを食べていたんだろう?



イエメンの料理って、どんな味付けが一般的なんだろう?



国民食があるって聞いたけど、どんな食べ物なの?
そんな風に現地の食事について、思いを馳せる方もいるかもしれません。
このセクションでは、かつて人々を魅了した豊かなイエメンの食の世界を探求していきましょう!
イエメンの基本料理と主食|ホブス・サルタ・オクダを解説
イエメンの食事は、「ホブス」と呼ばれるパンや米を主食とし、羊肉や鶏肉、魚、そして多彩なスパイスを使った煮込み料理が食卓の中心でした。
- ホブス (Khubz)
石窯で焼かれた、円くて平たいパン。様々な煮込み料理につけて食べられていました。 - サルタ (Saltah)
熱した石鍋で提供される、肉と野菜の煮込み。フェヌグリークという豆の泡状のペーストをかけて食べる、イエメンを代表する国民食です。 - オクダ (Oqda)
羊肉や鶏肉などを、トマトやジャガイモなどの野菜と一緒に煮込んだシチュー料理です。 - マンディ (Mandi)
スパイスで炊いたご飯の上に、じっくりと火を通した鶏肉や羊肉を乗せた、お祝いの席などでも食べられる人気の米料理です。



サルタ (Saltah)、熱々で美味しそう…
イエメンの食文化|地域性とスパイス
イエメンの料理は、オスマン帝国やインドのムガル帝国など、歴史的に関わりのあった地域の食文化の影響を受け、地域ごとに多様な発展を遂げていました。
共通しているのは、クミン、コリアンダー、カルダモン、ターメリックなど、多彩なスパイスをふんだんに使うことです。
この豊かな食文化が、紛争と人道危機によって深刻な影響を受けていることは、痛ましい限りです。
イエメンの飲み物文化|コーヒーの故郷
イエメンは、世界的に有名な「モカコーヒー」の故郷です。
コーヒー豆そのものではなく、コーヒーの殻をカルダモンやシナモンなどのスパイスと一緒に煮出した「ギシル」と呼ばれる飲み物が、日常的によく飲まれていました。
また、紅茶も人気があり、砂糖をたっぷり入れて甘くして飲むのが一般的でした。
かつて協力隊員として活動する中で、こうしたコーヒーやお茶に招かれることは、現地の人々と心を通わせる大切な時間でした。相手の厚意に感謝していただくことが良いマナーとされていました。



コーヒー発祥の地で、伝統的な飲み物を味わってみたかったですね。


青年海外協力隊イエメン:応募プロセスと帰国後のキャリアパス
「いつか、青年海外協力隊としてイエメンの復興に貢献したい!」
その熱い想いを実現するためには、まずイエメンに平和が戻ることが不可欠です。
ここでは、**現在は募集がない**ことを前提に、もし将来派遣が再開された場合に想定される一般的なプロセスと、協力隊経験がどのようにキャリアに活かせるかをご紹介します。
今はまだ遠い未来かもしれませんが、希望を持って、その日に向けた準備をイメージしてみましょう。
イエメン派遣への第一歩:応募から選考、派遣まで
イエメンへの派遣が再開された場合、以下のようなステップを踏むことになると考えられます。



もしイエメンへの派遣が再開されたら、何から始めればいいの?



派遣までのスケジュールって、どんな感じなんだろう?
そんなあなたの未来の疑問に答えるべく、一般的な応募プロセスをわかりやすい図でご紹介します。
年2回(春募集・秋募集)のタイミングでJICA海外協力隊のウェブサイトから応募します。
職務経歴や語学力などを基にした書類選考と、人物面や技術力を評価する面接が行われます。
2次選考から約2ヶ月後に合否が通知されます。合格者は候補者となります。
語学訓練(主にアラビア語)や国際協力、安全対策など、派遣に必要な知識とスキルを身につける合宿形式の訓練です。
訓練修了後、いよいよイエメンへ出発。約2年間のボランティア活動が始まります。
- アラビア語の学習
将来、イエメンや他の中東諸国で活動する際に、アラビア語能力は非常に大きな力になります。今から学習を始めることは、夢への大きな一歩です。 - 復興支援や人道支援に関する知見を深める
将来イエメンで求められるのは、復興に関わるスキルかもしれません。保健医療、水・衛生、教育、食料安全保障など、関連分野での経験や学習は必ず役に立ちます。
より詳しい応募条件や選考対策については、以下の完全ガイドをご参照ください。国は違えど、協力隊を目指す上での基本的な考え方は同じです。





合わせて2025年秋募集の要項や詳細を公式サイトから確認して見ましょう!
また、私はこの本を読んで青年海外協力隊に応募するための勉強をしています。
青年海外協力隊とは何なのか、実際に「コミュニティ開発隊員でフィリピンへ」「日本語教育隊員でドミニカ共和国へ」「看護師隊員でブルキナファソへ」派遣された方々の貴重な経験談など、知りたいすべてが盛り込まれています!
イエメンでの経験を未来へ:帰国後のキャリアと人生設計
もし将来、イエメンでの活動を終えた後、その経験はあなたの人生に何をもたらすでしょうか?



協力隊経験者の人たちって、どんな道に進んでいるの?



困難な状況での経験って、帰国後どう活かせるんだろう?



協力隊の経験って、具体的にどんな仕事に繋がるの?
イエメンでの活動経験は、もし実現すれば、他のどの国での経験とも比較にならないほど貴重なものになるはずです。
困難な環境で培った実践的なスキル、多様な価値観を受け入れる異文化理解力、そして数々の課題をクリアしてきた問題解決能力は、あなたの大きな財産となるでしょう。
ここでは、イエメンでの経験を輝かしい未来へと繋げるための方法を一緒に探すべく、青年海外協力隊に派遣された方々の今をご紹介します!
私が出会った!青年海外協力隊に派遣された方々の今
私は高校2年生の頃からずっと青年海外協力隊で国際協力をしたくて、とにかくいろんな情報を集めてきました。
そんな中で私が出会った、帰国後の青年海外協力隊の方々の現在をご紹介します。
Aさんはタンザニアに「コミュニティ開発」で派遣後、帰国してからは地元のJICAデスクで2年働き、その後アフリカの農家で起業をしました。



現在はクラウドファンディングも行って日本とアフリカの架け橋になっています!
地元のJICAデスクはたまたま後任がいなかったようですが、代々派遣後の隊員が2年の任期で行なっているそうです。
Bさんはコロンビアに『青少年教育』で派遣後、地元の大手商社に転職しました。
面接では、予測不能な環境で現地の人々と粘り強く交渉し、プロジェクトを成功させた経験が高く評価されたそうです。



キャリアアップもできて、スペイン語も習得して帰国できていて本当に理想的な進路ですね!
私が学んできたスペイン語と同じ言語圏に派遣されていたこともあり、たまにスペイン語で会話をしてくださいました!
Cさんは理系の会社で開発をしていましたが、マラウィ帰国後に地元の古民家を譲り受け、地域活性化にもつながるプロジェクトを行っています。



私が大学生の頃はよくボランティアに参加させていただき、一緒に茅葺き屋根を修復したり、水車を作ったりしました。
ずっと青年海外協力隊に行くことを目指してきましたが「現地で何のために派遣されたいのか」と問いかけてくれた彼のおかげで進路を決められました!
こんな感じに、私が知っている青年海外協力隊に派遣されていた方々は、世界をもっと良くできる、エネルギッシュで活動家の方が多かったです。
まだまだ多くの隊員たちの進路を聞いてきましたので、より詳しく青年海外協力隊派遣後のステップや就職の強みなどを知りたい方はこちらのブログをご参考ください!


まとめ:青年海外協力隊イエメン派遣は、平和な未来への希望
ここまで、現在は派遣が行われていないイエメンについて、過去の情報を基にご紹介させていただきました。
今回のブログでは以下の内容がわかりましたね!
- (紛争前の)青年海外協力隊のイエメン派遣の基本情報
- (過去の)青年海外協力隊イエメン派遣の職種と活動内容
- (紛争前の)イエメンでの生活シミュレーション!住居・食事・服装・文化について
- 現在の極めて厳しい治安状況と、将来派遣が再開された場合のプロセス
この記事を書くにあたり、イエメンの独自の文化や「幸福のアラビア」と呼ばれた豊かな歴史に触れる一方で、現在の深刻な人道危機を改めて痛感しました。青年海外協力隊の派遣が長年停止されているという事実は、その国の平和がいかに重要であるかを物語っています。
あなたの挑戦を、平和への祈りと共に
今すぐイエメンで活動することはできません。しかし、イエメンについて学び、関心を持ち続けることは誰にでもできます。
そして、国際協力への熱い想いを、今は派遣が行われている他の国で実現することもできます。まずはJICAの公式サイトで最新の募集要項をチェックし、応募のステップを以下の記事で完璧にマスターしましょう!





ここまで読んでいただきありがとうございます。



一日も早く、イエメンに平和が訪れることを願って。
ご来店ありがとうございました。